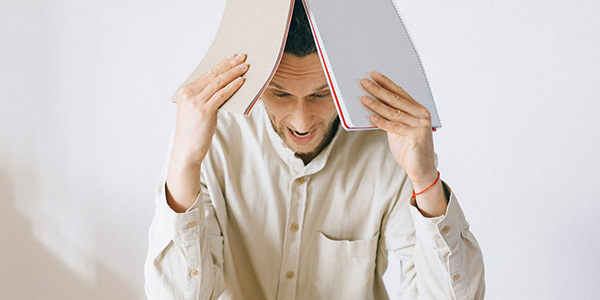毎年秋になると急に増える抜け毛。それは、ほんの数週間の生活環境によって起こるものではありません。
9月から11月にかけての抜け毛は、実は3、4ヵ月前の生活や出来事などが影響して起こっているのです。
なぜ太陽の日差しや紫外線が強い夏に多くならずに、秋になって急に増えてしまうのか。いきなり抜けて原因が分からないという方は、過去を振り返ってみましょう。
抜け毛は体調変化のサインでもありますので、放置せずにホームケアを行い薄毛予防に努めていきたいものですね。
今回は、9月以降急に抜け毛が増えるのは3、4か月前がポイントということをお伝えしながら今できる対策について解説します。

あなたの秋の抜け毛危険度はどのくらい?
9月や11月になって増える抜け毛は、その3~4ヵ月前の生活習慣だったり出来事だったりが影響しているといわれます。
そのため原因を探るには、夏の始まり頃から8月までを思い返してみましょう。
例えば、以下のようなことに心当りがないでしょうか。もし4個以上当てはまっていると感じた方は、秋の抜け毛の危険レベルが高まるといえそうです。

6月から8月の行動チェックリスト
■日焼け止めや帽子、日傘を使わず外出することが多かった
■シャンプー剤を適当に選び、洗髪も簡単に済ませていた
■連日冷えたビールを飲んだり、アイスを食べたりしていた
■焼き肉や揚げ物を食べる機会が多めだった
■頭皮がいつもより脂っぽいと感じていた
■冷房の効いた部屋にこもっていることが多かった
■夏バテして、食欲がなかった
■寝付けずに連日、深夜までテレビやスマホを見ていた
■夏休みが取れず、残業続きで寝不足だった
■お風呂はお湯に浸からずシャワーで済ませていた
以上に思い当たる項目が0~3個までの方は、ひとまず安心と言えるかもしれませんが、4~6個の方は、やや注意が必要、抜け毛が多くなる見込みなので生活習慣を見直してみましょう。
7個以上だった方は要注意。秋口以降は抜け毛が相当起こりそうで、数か月しても続くようなら進行性の脱毛症の可能性も考えた方が良いかもしれません。

秋の抜け毛の最大の理由は、夏の過ごし方にある?
ほんの数週間の生活の変化によって髪の毛が抜けるというわけではありません。
髪の毛が生えて成長し、抜け落ちるまで一定のサイクルがあります。男性の場合は2年から5年かけて成長し、徐々に停止していき完全に成長が休止してから3か月後に抜けていきます。
特にトラブルが無い方でも1日に50~100本位抜け毛はありますが、同じ量の毛が生まれているため全体量は一定に保たれています。
では、抜け毛の本数はいつ決定されるかということですが、それは髪の成長が休止した時点、つまり抜ける3か月前ということです。
つまり今日の抜け毛の数は、約3ヶ月前に決定されているというのです。
よく秋には毛が抜けるといわれますが、これも夏の始まる頃からの過ごし方によって決定されるのです。
そのため、6~8月の時期に紫外線を浴び過ぎた方や夏バテ、疲れ、季節の変化に伴う体調の乱れ、ストレスなどに自覚があればそれらが理由となります。
6~8月の紫外線による頭皮ダメージ
6月から8月にかけて紫外線の量と強さは最大にはっきされます。
外にいた時、頭がヒリヒリして、地肌が赤くなってしまった経験はありませんでしたか?夏休みに一日中遊んでいた時、頭皮が乾燥していると感じた方もいらっしゃると思います。
長時間はもちろん、短い時間でも紫外線を浴びていると頭皮は日焼けをしてしまいます。
それは、軽い火傷のような状態となり、かゆみや痛みを感じてしまうこともあったのではないでしょうか。
こういった紫外線は、頭皮を硬くするため血流が悪くなってしまうのです。頭皮の奥の発毛に関係する細胞にもダメージを与えしまい、3か月後の抜け毛の数を増やしてしまいます。そして2~3か月後(9月~11月)に結果として現れるのです。
だいぶ涼しくなってきた時に、抜け毛の本数が増えてしまうため、非常に不安になってしまいます。
夏バテによる栄養不足も影響する
紫外線の次に抜け毛の原因として多いのは、栄養不足です。
暑くて食欲が低下し、そうめんなど冷たくのど越しの良いものしか食べられなかったり、1日2食しか食べられなかったり、アイスを毎日食べてしまったり…。ということもあったかもしれません。
こういった食生活では、髪の発育に必要な栄養素であるタンパク質、ビタミン、ミネラルが全く足りていません。
血液によってバランスの良い栄養素が毛根細胞に運ばれることで初めて髪の毛は太く長く成長していきます。また、冷たいものを摂取すると慢性的な冷えが生じますから、新陳代謝の低下にもつながっていきます。
6月頃から軽い栄養不足状態や新陳代謝の低下が慢性化していたとすると、その結果が秋に髪の毛がドっと抜けてしまうケースもあります。
秋の抜け毛をこれ以上増やさないためのケアは?
数か月前から気を付けて生活することが一番ですが、すでに受けてしまったダメージは、戻すことはできません。
そのため、今後の抜け毛の本数を減らすことや頭皮環境の悪化を軽減することに努めましょう。その代表的な3つのケアをご紹介します。
刺激が少ないアミノ酸シャンプーに切り替える
シャンプーにも様々な種類がありますが、最も頭皮への刺激が少ないのは、アミノ酸系シャンプーです。
夏の間は、ひんやり爽快感のある高級アルコール系シャンプーを使っている方が多いのではないでしょうか? お風呂上りに涼しくさっぱりするので使いがちですが、頭皮にも髪の毛にも刺激が強くおすすめできません。
アミノ酸シャンプーは、洗浄能力が優しく配合成分も低刺激のため、シャンプーによる抜け毛を軽減することができます。
しっかり汚れが落ちないのではないかと思う方もいらっしゃるのですが、効果的な洗い方をすれば問題はありません。そのポイントは、2度洗いすること。
洗う際は、シャンプー剤をまず髪の毛だけになじませ、サッと洗いすすぎます。
再度シャンプーを取って、今度は髪の毛と頭皮に軽くなじませ指の腹で優しくマッサージしながら洗って下さい。ダメージも少なく効果的に汚れを落とすことができるでしょう。
頭皮マッサージを取り入れ血行促進!
毛根まで血液を届けることは抜け毛、薄毛予防としてはとても大切です。
そこでおすすめでしたいのが頭皮マッサージ。正しく行うことで血行が良くなり毛根部分に多くの栄養を届けることができるようになります。
継続的に行えば、頭皮のたるみを防いで髪にハリやコシが戻ってきますし、丈夫な髪が生えるようになり髪の毛の抜け過ぎも解消されるでしょう。
注意したいのは、強引に力を入れて過ぎること。毛細血管まで傷つけることになり、9~11月の抜け毛を増やす危険もありますので、あくまで優しくタッチする感覚で行って下さい。

髪の毛に良いものを食べる
タンパク質にビタミン類、海藻類、亜鉛などなど髪に良いとされる栄養素があります。
ただ、すぐにどの食材を献立に取り入れれば良いか思い浮かばないという方も多いと思います。そのような時におすすめの方法をご紹介します。
「ま・ご・わ・や・さ・し・い」という言葉をご存じですか?
これは食べ物の頭文字を並べたもので、これらに従って食べ物を摂ることを意識するだけでも自然とバランスの取れた食事になり予防につながります。
「ま」は豆、「ご」はゴマ、「わ」はワカメ、「や」は野菜、「さ」は魚、「し」は椎茸、「い」は芋という具合に、これらを組み合わせた食事を摂れば頭皮の成長に必要な栄養素を十分に吸収、抜け毛の予防も期待できるでしょう。
また、旬のものを食べるとより高い栄養が摂れますので、秋は旬食材と「まごわやさしい」を心掛けて食卓に登場させてみてはいかがでしょうか?
まとめ
9〜11月には数か月前のダメージによる抜け毛が増えることをお伝えしてきました。秋に起きる抜け毛の原因が分からなかった方は一度、過去を振り返ってみましょう。
思い当たる節があれば、ホームケアで頭皮をいたわり抜け毛予防に努めていきましょう。
夏のダメージだけでなく、別の原因で異常に抜け毛が多く薄毛が目立つようになってくる場合があります。
例えばAGAや皮膚炎によるもの、ストレスによるものなどがあります。その場合は、季節性のものとは原因が全く異なるもので、秋の抜け毛は自然に収まりますがそうでない場合はそのまま進行し続けていきます。
ご自分で判断せず、一度専門家に相談して早急に対応した方が良いでしょう。